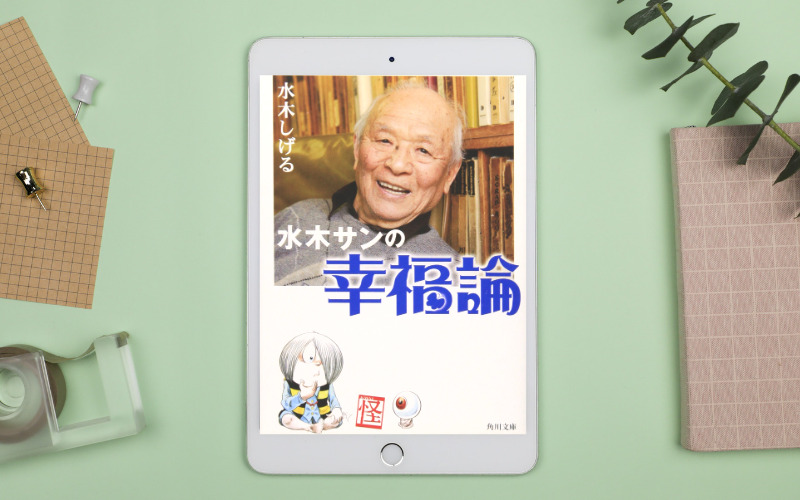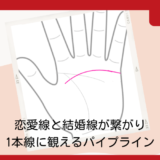この記事には広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
スポンサーリンク
あちらの世界に旅立った水木先生
もしかして死なないんじゃないか?と、本人さへ思っていた水木しげる先生が、とうとうアチラの世界に旅立たれました。今頃、妖怪仲間と楽しくコッチの世界を観ていることと思います。
そんな水木先生の訃報が流れたと同時にネットに流れてきたのが、水木先生の『幸福の7か条』でした。⇒水木しげる『幸せになるための七カ条』が話題! 年の初めに読んでおきたい!
せっかくなので、この7か条が掲載されている本を買って読んでみました。
水木さんの幸福の七か条
- 第一条 成功や栄誉や勝ち負けを目的に、ことを行ってはいけない。
- 第二条 しないではいられないことをし続けなさい。
- 第三条 他人との比較ではない、あくまで自分の楽しさを追及すべし。
- 第四条 好きの力を信じる。
- 第五条 才能と収入は別、努力は人を裏切ると心得よ。
- 第六条 怠け者になりなさい。
- 第七条 目に見えない世界を信じる。
スポンサーリンク
水木サンのルールに倣って、パナセさんのルールを作ろうと思ったわ。
この本は、「第一部 水木サンの幸福論」「第二部 私の履歴書」と二部構成になってます。「第一部 水木サンの幸福論」は、【幸福の7か条】を順番に説明しています。
水木さんは、自分のことを「水木サン」と呼びます。そして、赤ちゃんではない子供全般のことを「ベビィ」と呼びます。まず、この表現からして、「水木さんだなー(・∀・)」って感じです。
この【幸福の7か条】が出てきたキッカケは、日本経済新聞の「私の履歴書」に連載中に、ついウッカリ「じつは幸福観察学会というのを作って、会長をやってます」と書いてしまったことで、方々から水木さんの幸福論が読みたいとの反響が多くきたので、この本で発表することになったそうです。
第二部を読むと幼年時代からの水木さんを知ることができますが、小さなころからずっと「幸福って何だろう?」と自問自答しつづけてきた結果、生まれたのが【幸福の7か条】だそうで。【水木サンのルール】で生きてこられた水木さんならではの【幸福の7か条】が、この忙しい俗世に生きる私たちに新たな視点を与えてくれています。
「特別付録1 わんぱく三兄弟、大いに語る」の中に記載されてますが、水木さんは少年の頃、死体に異様な程の関心を持ち、「人間は死ぬとき、どんなふうになるんだろう」と考えて、弟の幸夫さんを本気で海に突き落とそうとまでしたそうです。小さいころ、両親にちょっと頭の足りない子と思われていた一端が垣間見れますね。(笑)
「第一部 水木サンの幸福論」も面白いですが、「第二部 私の履歴書」は、幼少の頃から戦争体験、戦後いろいろなことをして稼いでた時期、”水木しげる”になったいきさつ、結婚、売れ始めて貧乏神がいなくなった話とかとか。どのお話しもとても面白かったです。
水木さんの中には、いつでも【水木サンのルール】というのがあって、このルールが、なんとも羨ましく愛おしさを感じさせます。私も、水木さんに倣って、”パナセさんのルール”と構築していこうと思います。
自分なりのルールができれば、それこそ【幸福の7か条】の【第六条 怠け者になりなさい。】に沿った生き方が出来そうな気がします。(・∀・)
生命線が短くて早死にすると思ってたのに、戦争で生き延びたら生命線が伸びていたらしい。
手相観として興味深い文章がありました。「第二部 私の履歴書」の「7 憂鬱な毎日」の中から抜粋します。
私には「長生きできない」という思いがこびりついていた。小学校三年生ぐらいのとき、兄弟三人で盗み見た婦人雑誌に手相の記事が図解入りで載っていた。自分の手のひらを眺めると、何と生命線が兄や弟の半分ぐらいしかない。途中でぷっつりと切れているのだ。早死にするという恐怖心が心の中に棲みついたのはそれからだった。
水木さんは、生命線の短さから、自分は早死にすると思っていたそうです。そのせいもあって、「死んだらどうなるのか」と興味を持ったのかもしれません。
それから、戦争に行き、片腕を負傷してジャングルの中で終戦を迎えたました。終戦を迎えたものの、すぐには日本に帰れず、しばらくの間は、ジャングルの中で過ごしていたそうで、その時、現地のトライ族と仲良くなり、毎日、その部族の元に行ってたそうです。
「13 トライ族との日々」の中から抜粋
漆黒の闇の中で、美しい星々を見ていると、私が九死に一生を得たのは、大自然にいる、何か大きいものに守られたからだと思った。それは神かもしれないし、精霊だったかもしれない。手のひらを眺めると、途中で切れていた生命線がいつの間にかつながり、長く延びているのに気が付いた。
戦争を生き抜いたことで、フト気づけば、生命線が伸びていた。って、なんとも不思議なことですよね。でも、こういったことはアリアリです。本当に手相って変わりますからね。
それに、実際に水木さんは見えない存在に助けられたのだと思います。それは、水木さんのご先祖様や現地の精霊(妖怪)などだと思います。
手相のことなんて、なんの期待もせずに読んでいたら、手相の話が出てきて、ちょっと嬉しくなりました。いや、喜ぶものでもないんでしょうが。(笑)
「幸せってものは、体と心で感じてこそ初めて分かるんだ。」
この本の中で、私が1番印象に残ったのは、娘さん(悦子さん)の書かれた解説【父と「幸せ」】でした。父親・夫としての顔や水木さんの人間としての素の表情が見えて、とても素敵なお話です。
悦子さんが12歳の頃、いじめにあっていて、本気で死ぬことを考えていたそうです。その時、水木さんが「人の幸福の量」について書いた本を読んでいて、ある日の夜の食卓で、「人の一生のうちの幸せの量も不幸の量も、ある程度決まっているそうだ。すなわち、不幸だけではない。不幸もあれば幸せもおなじぐらいあるってことだよ。」と呟いた。
落ち込んで死ぬことを考えていた悦子さんにとって、この言葉は、まさに暗闇の中の一筋の光。その後、悦子さんは水木さんの書斎に飛び込み、父である水木さんと会話をしたことで、死ぬことを選びませんでした。
一部、抜粋します。
悦子「でもさ、ものすごく苦しくなってしまったら死んでもいいんじゃないのかな?死ねばその苦しみから解放されるんだもの」
水木「バカだなぁ。死んでしまっては何もならんよ。幸せってものは生きてこそ感じられるんだ。噛みしめられるんだよ。考えてみろ。死んでしまったら肉体がなくなって魂だけになるだろ。魂だけになったら幸せを実感できないんだよ。幸せってものは、体と心で感じてこそ初めて分かるんだ。」
悦子「じゃあ私はこの先、生きていて幸せになれるのかな」
水木「そんなのお父ちゃん神サンじゃないから分からんよ。なぜならお前の幸せは、お前にしか解らんのだから。生きておればいずれ分かる。な、悦子」
ポンッと私の肩を叩きながら父は私に言った。
そんな父の言葉で今の私がある。小学生のうちに死なずにすんだのだ。
素敵な会話ですよね~。悦子さんを一人の人間として見ているのが伝わります。上から目線な人だと、こんな返事はしないと思うんですよね。この章では、水木さんと奥様の愛らしい様子も書かれていて、思わず微笑んでしまいます。
妖怪か人間か分からないような奇人変人ぶりを発揮しながらも、「奇人は貴人」と言い切る人間味も妖怪味もあふれた水木さん。今は、馴染みの妖怪たちと楽しく踊りあかしていることでしょうね。
スポンサーリンク